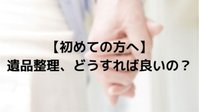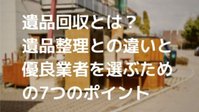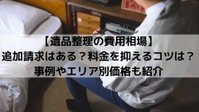遺品整理時には捨ててはいけないものが複数あり、闇雲に処分するのはNGです。
誤って貴重品や重要書類を捨ててしまうと、相続時にトラブルが起こるケースも。保管方法や万が一捨ててしまった場合の対応なども含めて解説します。

- 遺品整理で闇雲に物を捨ててはならない理由
- 遺品整理で捨ててはいけない10個のもの
- 遺品整理時に捨ててはいけないものを守る方法
- 捨ててはいけないものを万一処分してしまった場合の対応
- 捨ててはいけないものを保管する際のポイント
- 捨ててはいけないもの以外の処分方法
- 遺品を処分するときの注意点
- まとめ
ご実家のお片付けにお困りですか?
みんなの遺品整理では、全国881社の優良遺品整理業者から
複数業者の相見積もり・全国即日対応可能
お急ぎの方はお電話にてご相談ください!
通話無料
みんなの遺品整理 お客様相談窓口
0120-905-734受付時間 8:00~19:00 (土日祝も対応)
相談無料
- 複数見積もり可(最大3社)
- 買取対応などの相談も◎
- 即日・最速対応業者をご案内
遺品整理で闇雲に物を捨ててはならない理由
|
遺品整理で闇雲にものを捨てると、さまざまなトラブルに繋がる恐れがあります。
特に思い出の品などは、お金を払っても取り戻せません。後々の後悔がないよう、ひとつずつ丁寧に仕分けましょう。
作業を早く終わらせたいからと言って焦りは禁物です。遺品整理に充てる時間が確保できない場合は、無理をせず業者への依頼を検討する方法もあります。
遺品整理で捨ててはいけない10個のもの
|
遺品整理で捨ててはいけないもの一覧チェックリスト |
遺品整理時に上記のアイテムを見つけた場合は捨てないように注意しましょう。手放すと将来後悔する可能性が高いため、大切に保管します。
遺言書

法的な効力を持つことに加えて、故人の希望が書かれている場合もある遺言書は必ず保管します。遺品整理を始める前にまず遺言書の有無を確認しましょう。
書面だけでなく、録音やメールといった形式で残されている遺言も大切に管理します。
誤って捨てると、親族同士が揉める原因になることも。円滑に遺品整理を進めるためにも、大切に取り扱いましょう。
財産関連のもの

銀行の通帳や印鑑、証券などは相続などの観点においても非常に重要なものです。
通帳を捨ててしまうと相続人や遺族でも引き出しが困難になります。
スムーズに相続するためにも、下記の財産関連のものは慎重に取り扱いましょう。
| 保管しておくべき財産関連のもの |
|---|
|
仕事関係の書類

故人の仕事関係の書類は一定期間捨てずに取っておくのがおすすめです。
うっかり処分してしまうことで、損害が及ぶなどのトラブルに発展する可能性も捨てきれません。
会社に問い合わせて、不要な旨が確認できるまで保管しましょう。
ヘソクリなどの現金

故人がヘソクリや現金をタンスなどにしまっていると、気づかずに捨ててしまうことがあります。
現金は法律上捨ててはいけません。相続の対象にもなるため、すべて残しておく必要があります。
遺品整理時は袋や封筒など、中身をひとつずつ確認しましょう。面倒だったり、時間がなかったりする場合は遺品整理業者に依頼するのがおすすめです。
身分証明書

身分証明書は利用していたサービスの解約手続きなど、何かと有用なため保管します。公共料金の領収書やクレジットカードなども一旦残しておきましょう。
故人宛ての手紙や年賀状も貴重な情報源になるため、捨てずに管理します。
誤って捨てるとサービスが解約できずに請求が続く懸念もあるため、注意しましょう。
デジタル遺品

スマートフォンやパソコンのデータなどのデジタル遺品も消去せずに保存しておきます。
暗号資産やネット証券はIDやパスワードが必要になるケースもあるため、しっかりと記録しておきます。
相続の対象になることもあるため、確認せずに消すとトラブルにつながるリスクも。大切に保管しましょう。
返却の必要があるもの

レンタル品やリース品などは捨てずに返却しましょう。誤って処分した場合、損害金が発生するリスクもあります。
運転免許証やパスポート、クレジットカード、保険証なども本来返却が必要なものです。有効期限を迎えれば失効しますが、遺品整理時に返却すると安心です。
誤って捨てると損害賠償請求をされたり、遅延金が発生したりする可能性があるため、確実に返却しましょう。
鍵

家や自動車、倉庫などの鍵は不要なことが明確になるまでは捨てずに保管しておきましょう。
賃貸の退去時や、持ち家や車の売却時に鍵の交換費用がかかるなど、出費の原因になります。
倉庫や金庫内の物を取り出せなくなる可能性もあるため、注意して扱います。
買い取ってもらえる可能性があるもの

美術品や骨董品といった古美術品をはじめ、フィギュアやブランド品、和服など買い取ってもらえる可能性があるものも残しておきましょう。
鑑定に出した後に値打ちのあるものだったことがわかるケースも少なくないため、闇雲に捨てないようにします。
相続の対象になる場合もあり、独断で処分するとトラブルに繋がる懸念も。闇雲に捨てるのはNGです。
思い出の品物

故人の写真や思い出の品物は、データ化するなど工夫して残すのがおすすめです。特に写真はアルバムで保管すると、どうしても場所を取ってしまいます。
現物の上限を決めたうえで、残りはデータとして保管しましょう。
思い出の品や写真は捨てると復元は困難です。安易に捨てないように注意しましょう。
遺品整理時に捨ててはいけないものを守る方法
遺品整理時に捨ててはいけないものを守るにはいくつかの方法があります。開始前に確認しておけばトラブルも防げるでしょう。
生前に話し合う

可能であれば、ご家族が元気なうちに重要なものの取り扱いに関してしっかりと話し合っておくのがベストです。
話し辛い内容ではありますが、後々のリスクヘッジという意味でも情報を共有しておくことをおすすめします。
エンディングノートを確認する

エンディングノートがある場合は、確認することで大切なものを捨てずに済みます。エンディングノートとは、故人の希望や捨ててはいけないものの保管場所など、さまざまなことを記録できるノートです。
遺書を確認する

遺書や遺言書がある場合は、遺品整理前に読むことで大切なものを捨てずに守れます。相続とも関係する書類のため、トラブルを防ぐ意味でも遺品整理を行う前に必ず確認しましょう。
遺品整理士に依頼する

遺書やエンディングノートなどが見つからずに困っている方は、遺品整理士のいる業者に依頼するのがおすすめです。
遺品を適切に整理してくれるほか、保管するべきものについてのアドバイスも貰えます。整理中に遺書やエンディングノートが見つかるケースもあります。
捨ててはいけないものを万一処分してしまった場合の対応
捨ててはいけないものを意図せず処分してしまったり、失くしたりしてしまう可能性もゼロではありません。万が一のときに落ち着いて行動するための対応策を解説します。
遺言書を捨ててしまった場合
遺言書を捨ててしまったときの対応は、当該書類が公正証書遺言書かどうかによって異なります。
故人が公正証書遺言を作成していた場合、原本が公証役場に預けられているため、自宅の遺言書を処分してしまっても再発行が可能です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、原則遺言書はないものとして扱われます。
財産関連のものを捨ててしまった場合
通帳を処分してしまった場合は金融機関へ問い合わせしょう。故人に関する質問をされるので回答します。住所、氏名、生年月日をすぐ言えるようにしておくと安心です。
証券が無い場合は、保険会社から定期的に届くお知らせ書類や生命保険料控除証明書の有無を確認します。有料にはなりますが、生命保険契約照会制度でも内容を確認可能です。
返却の必要があるものを捨ててしまった場合
レンタル品など返却の必要があるものを捨ててしまった場合は、気づいた時点で貸主に連絡します。
契約者が亡くなったため解約する旨と誤って処分したことを伝えましょう。その後の対応は業者によって異なります。
上記以外のものを捨ててしまった場合
現金や古美術品、思い出の品などは処分してしまうと、ほとんどの場合取り戻すのが不可能です。誤って捨ててしまわないように注意しましょう。
プロの遺品整理業者であれば細心の注意を払って作業してくれるため、大切なものを失くす心配もありません。
捨ててはいけないものを保管する際のポイント
捨ててはいけないものについては、上手に保管するためにいくつかのコツがあります。
物が増えすぎたり、管理可能なキャパをオーバーしたりするのを防ぐためにもチェックしておきましょう。
思い出の品を残し過ぎない
思い出の品を残しすぎるとスペースを圧迫してしまいます。残す物量の上限を決めて、管理できる範囲のものだけを残します。
どうしても捨てられない場合は、ある程度残した後、段階的に処分する方法もあります。
支払い通知は速やかに処理、分別する
公共料金や各種サービスの支払い通知などは見つけた段階で速やかに手続きしましょう。
対応が済んだ物から処分するのがおすすめです。手続き済みのものと未処理のものが混同する心配もありません。
写真はデータ化する
写真はアルバムのまま残すとスペースをとるため、データ化するのがおすすめです。
現物のまま残した結果、保管場所に困るケースは少なくありません。DVDやUSB、クラウド上などに保存するのが望ましいでしょう。
先祖から受け継いできたものの処分は親族と話し合う
先祖から受け継いできたものは独断で判断・処分せず、必ず親族同士で話し合いましょう。コミュニケーションを取ることで、価値のあるものを誤って処分するリスクも軽減できます。
捨ててはいけないもの以外の処分方法
処分すると決めたものでも闇雲に捨てて良いわけではありません。遺品整理をスムーズに進めるためにも適切な処分方法を理解しておきましょう。
寝具類
故人が使用していた寝具は、衛生状態が良くない場合もあるため捨てましょう。
各自治体ごとに設定されているルールに沿って処分します。介護用品としてリースされていたものなどは、洗濯して綺麗にしたうえで返却します。
書籍、コレクション
書籍は古本屋で買い取ってもらったり、図書館へ寄付したりする方法があります。
フィギュアやおもちゃなどのコレクションは、付属品などを揃えたうえでリサイクルショップに持ち込むと良いでしょう。
家電
まだ使える冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの家電はリサイクルショップに買い取ってもらうのがおすすめです。
使えないものは各自治体のルールに則って処分します。パソコンやデジカメの場合、必ず初期化やデータの消去を行いましょう。
家具類
タンスなどの家具類は、残したいもの以外はリサイクルショップに持ち込むか、出張買い取りを依頼するのがおすすめです。
まだ使えるからと持ち帰っても、自宅のインテリアになじまず、最終的に処分するケースも少なくありません。
遺品を処分するときの注意点
不用な遺品を処分する際にもいくつかの注意点があります。意図せずルールを破って不法投棄になってしまうなどの事態を防ぐためにも、しっかりと確認しておきましょう。
自治体のルールに従う
ゴミ処理などのルールは自治体によって異なるため事前に確認しましょう。
引き取り日時についての事前相談が必要など、さまざまなルールがあります。不法投棄に該当しないためにも自治体の決まりは入念にチェックしましょう。
タイミングに注意する
遺品を整理したり処分したりする適切なタイミングは故人の状況によって異なります。
具体的には、血縁関係の有無や故人の住環境が賃貸住宅か持ち家かなどの要素です。上記次第で、どの程度遺品整理に関わるべきかも異なるため注意しましょう。
遺品整理業者を利用する
遺品整理や処分方法がわからなかったり、思うように進まなかったりするときは、無理せずプロの手を借りる方法もあります。
遺品の仕分けやごみの処分などには、大変な時間と労力が必要です。遺品整理業者であれば迅速かつ確実に作業を進めてくれるほか、ご家族の負担も大きく軽減できます。
まとめ
遺品整理時には捨ててはいけないものが一定数存在するため、闇雲に処分するのはNGです。再発行できる書類などもありますが、中には2度と手元に戻ってこないものもあるため慎重に進めましょう。
遺品整理は労力を伴う作業であることも事実なので、無理をせず業者に依頼するのもおすすめです。
「みんなの遺品整理」では全国の遺品整理業者を紹介中。遺品整理士認定協会の相談員が、相談対応から業者選びまで徹底的にサポートします。
遺品整理を検討中の方は「みんなの遺品整理」をチェックしてください。
【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】
遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。
遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。
法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟。法規制を守り、遺品整理業務を真摯に行っている企業の優良認定、消費者保護のための遺品整理サービスガイドラインの制定もおこなっている。
【執筆者:みんなの遺品整理事務局】
東証プライム市場上場の株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営しています。2017年より業界最大級の遺品整理・実家の片付け業者の比較サイト「みんなの遺品整理」を運営し、全国で累計件数30,000人以上の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。
はじめての遺品整理でも、専門知識が豊富な相談員が中立な立場で、無料アドバイスをさせていただきます。大切な人の生きた証を残しつつ、気持ちよく次の世代へ資産や遺品を引き継ぐために、私たちは、お客様一人一人に最適なお手伝いができる情報提供・業者のご提案を致します。
ご実家のお片付けにお困りですか?
みんなの遺品整理では、全国881社の優良遺品整理業者から
複数業者の相見積もり・全国即日対応可能
お急ぎの方はお電話にてご相談ください!
通話無料
みんなの遺品整理 お客様相談窓口
0120-905-734受付時間 8:00~19:00 (土日祝も対応)
相談無料
- 複数見積もり可(最大3社)
- 買取対応などの相談も◎
- 即日・最速対応業者をご案内