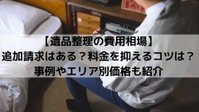生活保護の受給者が死亡した場合、アパートの退去費用は誰が払うのか曖昧な方は少なくありません。基本的に連帯保証人や相続人が支払いますが、不在の場合もあるでしょう。実際の事例や費用を抑えるポイントも解説するので、あわせて参考にしてください。

- 生活保護受給者が死亡したらアパートの退去費用は誰が支払う?
- 生活保護受給者が死亡した場合のアパートの退去費用はいくら?
- 生活保護受給者が死亡した場合のアパートの退去費用を抑えるポイント
- 生活保護受給者が死亡した場合にアパートの退去以外にかかる費用
- 【事例で紹介】アパートで起きた孤独死の片付けにかかった費用
- まとめ
生活保護受給者が死亡したらアパートの退去費用は誰が支払う?
| 1.連帯保証人→2.相続人→3.物件の所有者や行政 |
生活保護の受給者が死亡した場合、アパートの撤去費用上記の順に支払い義務が発生します。
相続放棄で相続人がいなかったり、身寄りがなかったりする場合は行政や自治体、物件のオーナーが費用を負担することもあります。
出典:総務省行政評価局「地方公共団体における遺品の管理に関する事例等(遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書別冊)」(PDF)
生活保護受給者が死亡した場合のアパートの退去費用はいくら?
遺品整理を行う場合
| 間取り | 料金相場 | 作業人数 | 作業時間 |
|---|---|---|---|
| 1R・1K | 30,000円~80,000円 | 1~2名 | 1~2時間 |
| 1DK | 50,000円~120,000円 | 2~3名 | 2~4時間 |
| 1LDK | 70,000円~200,000円 | 2~4名 | 2~6時間 |
| 2DK | 90,000円~250,000円 | 2~5名 | 2~6時間 |
| 2LDK | 120,000円~300,000円 | 3~6名 | 3~8時間 |
| 3DK | 150,000円~400,000円 | 3~7名 | 4~10時間 |
| 3LDK | 170,000円~500,000円 | 4~8名 | 5~12時間 |
| 4LDK以上 | 220,000円~600,000円 | 4~10名 | 6~15時間 |
※みんなの遺品整理に掲載されている800社以上の業者のホームページ、3万人以上の実際に利用した金額データから算出しています。
(2024年4月7日時点)
※ゴミ屋敷のような状態、特殊清掃が必要だと料金が変わります。
特殊清掃を行う場合
| 間取り | 特殊清掃作業時間 | 消臭時間 | 特殊清掃・消臭作業代 |
|---|---|---|---|
| 1R | 1.5時間 | 4時間 | 60,000円 |
| 1R | 3時間 | 6時間 | 60,000円 |
| 1DK | 4時間 | 48時間 | 60,000円 |
| 1R | 4時間 | 12時間 | 80,000円 |
| 1R | 2.5時間 | 72時間 | 95,000円 |
遺品整理+特殊清掃を行う場合
| 間取り | 料金相場 | 作業人数 | 作業時間 |
|---|---|---|---|
| 1R・1K | 90,000円~175,000円 | 1~2名 | 1~3時間 |
| 1DK | 110,000円~215,000円 | 2~3名 | 2~4時間 |
| 1LDK | 130,000円~295,000円 | 2~4名 | 2~6時間 |
| 2DK | 150,000円~345,000円 | 2~5名 | 2~6時間 |
| 2LDK | 180,000円~395,000円 | 3~6名 | 3~8時間 |
| 3DK | 210,000円~495,000円 | 3~7名 | 4~10時間 |
| 3LDK | 230,000円~595,000円 | 4~8名 | 5~12時間 |
| 4LDK以上 | 280,000円~695,000円 | 4~10名 | 6~15時間 |
※上記金額は作業費を含む人件費・車両費・回収運搬費・廃棄物処分費をあわせた概算費用となります。
※ゴミ屋敷清掃や特殊清掃が必要な現場の場合、料金が大きく変わります。
生活保護の受給者が亡くなってアパートを退去する際には、原状回復費用を含む遺品整理や特殊清掃費用がかかります。
孤独死の場合は特殊清掃が必要になり、消臭などの作業を行います。また、清掃費用以外に退去日までの家賃も支払う必要があるでしょう。
生活保護受給者が死亡した場合のアパートの退去費用を抑えるポイント
生活保護の受給者が死亡した場合のアパートの撤去費用を抑えるには2つのポイントがあります。できる限り出費を防ぐためにも把握しておきましょう。
できる限り早く対応する
アパートの退去費用を抑えるには、できるだけ早く対応することが先決です。早い時期に解約手続きを行うことで退去日までにかかる家賃を最小限に抑えられます。
ライフラインや駐車場などの解約も早期に行うことで、無駄な出費を防げるでしょう。
業者選定は慎重に行う
思わぬ出費を防ぐには、片付けを依頼する業者の選定を慎重に行うことも重要です。
悪徳業者に引っかかると作業後に追加料金を請求されるなどの被害を受ける恐れがあります。必ず複数業者から見積もりを取り、費用感を把握しながら慎重に業者を選びましょう。
生活保護受給者が死亡した場合にアパートの退去以外にかかる費用
|
・葬儀費用 |
生活保護の受給者が死亡した場合、アパートの退去費以外にも費用が発生します。葬儀費用をはじめ、お布施や各所への交通費など支出は少なくありません。
特定の条件を満たす場合、葬儀費用を負担してもらえる葬祭扶助制度を利用できることもあります。
【事例で紹介】アパートで起きた孤独死の片付けにかかった費用
孤独死が起きたアパートの遺品整理を行った事例

出典:みんなの遺品整理掲載業者「遺品整理・特殊清掃リライブル」事例紹介
| 費用 | 120,000円 |
|---|---|
| 作業時間 | 3~4時間程度 |
| 作業人数 | 2名 |
消臭清掃がなく遺品整理もある程度済んでいた事例です。家財の改修やゴミの分別・処理を中心に行い短時間で作業が完了しました。
孤独死が起きたアパートの特殊清掃を行った事例

出典:みんなの遺品整理掲載業者「遺品整理専門会社クリーンメイト」事例紹介
| 費用 | 115,000円 |
|---|---|
| 作業時間 | 約6時間 |
| 作業人数 | 3名 |
孤独死から1週間が経過したアパートの清掃例です。悪臭除去や室内消毒などの特殊清掃が主な作業となりました。ウジ虫が発生しており、壁紙やフローリングも張替えました。
まとめ
生活保護の受給者が死亡した場合、アパートの退去費用は連帯保証人や相続人に支払いの義務があります。
相続放棄や身寄りがない場合は物件のオーナーや行政が対応するケースもあるでしょう。出費を最低限に抑えるためには、できる限り早く片付けや手続きを済ませることが大切です。
「みんなの遺品整理」では、アパートの退去に向けた片付けを依頼できる業者を多数掲載中。状況に合わせて最適な作業を実施しています。悪徳業者もゼロなので安心して依頼できますよ。
【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】
遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。
遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。
法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟。法規制を守り、遺品整理業務を真摯に行っている企業の優良認定、消費者保護のための遺品整理サービスガイドラインの制定もおこなっている。
【執筆者:みんなの遺品整理事務局】
東証プライム市場上場企業の株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営しています。2017年より業界最大級の遺品整理・実家の片付け業者の比較サイト「みんなの遺品整理」を運営し、全国で累計件数30,000人以上の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。
はじめての遺品整理でも、専門知識が豊富な相談員が中立な立場で、無料アドバイスをさせていただきます。大切な人の生きた証を残しつつ、気持ちよく次の世代へ資産や遺品を引き継ぐために、私たちは、お客様一人一人に最適なお手伝いができる情報提供・業者のご提案をいたします。