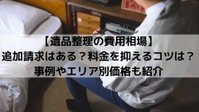親の家の片付けをどうするか頭を悩ませている方は少なくありません。親の家を片付けるとさまざまなメリットがある一方、空き家状態の実家を放置すると多くの弊害があります。
片付けの必要性から、実際に整理した人の声までご紹介します。

ご実家のお片付けにお困りですか?
みんなの遺品整理では、全国881社の優良遺品整理業者から
複数業者の相見積もり・全国即日対応可能
お急ぎの方はお電話にてご相談ください!
通話無料
みんなの遺品整理 お客様相談窓口
0120-905-734受付時間 8:00~19:00 (土日祝も対応)
相談無料
- 複数見積もり可(最大3社)
- 買取対応などの相談も◎
- 即日・最速対応業者をご案内
親の家は片付けたほうがいい?
空き家の放置には倒壊や近隣とのトラブル、不法侵入などさまざまなリスクがあり、国土交通省も積極的な対応を求めています。
放置を続けると、固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなるため、必要がある場合は片付けましょう。
親の家を片付けるメリット
親の家を片付けると複数のメリットがあります。行動に移すうえでのモチベーションにもなるので、まずは片付けるべき利点を把握することから始めましょう。
ご近所トラブルを防げる

親の家を片付けることで、ご近所トラブルの防止に繋がります。放置することで悪臭を放ったり、ネズミなどの害虫が近隣住宅にまで侵入したりしてトラブルに発展するケースもあります。
犯罪のリスクを抑えられる

親の家を片付けることで犯罪リスクの防止にも繋がります。空き家状態を放置して、壊れた窓から不法侵入者に出入りされるケースもあります。
周辺地域の治安が悪化する原因にもなるため、必要がある場合は片付けるようにしましょう。
住環境を整えられる

実家を片付けることでご両親が暮らしやすくなるような環境を整えられます。
探しものが見つかりやすくなったり、いざという時の避難経路を確保しやすくなったりします。転倒や落下物の防止にも役立つでしょう。
リフォームや売却などが円滑に行える

親の家を片付けると、リフォームや売却などを円滑に進められます。バリアフリー化などのリフォームや売却するにあたって、家屋内は整理しておく必要があります。
スペースを確保することで工事や査定もスムーズに行えるでしょう。
親の家を片付ける方法
|
・片付け業者に依頼する |
親の家の片付けは基本的に自力で対応するか業者に依頼するかの2択になります。
一口に親の家の片付けと言っても、親御さんが存命のうちに行う生前整理や、没後に行う遺品整理などさまざまな状況があります。
いずれの場合も自力で対応するか、業者に依頼するかの選択肢から最適なものをチョイスすることになるでしょう。
ただし、セルフネグレクトなどで実家がゴミ屋敷化している場合は自力での作業は困難なため、専門業者に依頼するのが適切です。
親の家の片付けにかかる費用
| 間取り | 料金相場 | 作業人数 | 作業時間 |
|---|---|---|---|
| 1R・1K | 30,000円~80,000円 | 1~2名 | 1~2時間 |
| 1DK | 50,000円~120,000円 | 2~3名 | 2~4時間 |
| 1LDK | 70,000円~200,000円 | 2~4名 | 2~6時間 |
| 2DK | 90,000円~250,000円 | 2~5名 | 2~6時間 |
| 2LDK | 120,000円~300,000円 | 3~6名 | 3~8時間 |
| 3DK | 150,000円~400,000円 | 3~7名 | 4~10時間 |
| 3LDK | 170,000円~500,000円 | 4~8名 | 5~12時間 |
| 4LDK以上 | 220,000円~600,000円 | 4~10名 | 6~15時間 |
※みんなの遺品整理に掲載されている800社以上の業者のホームページ、3万人以上の実際に利用した金額データから算出しています。
(2024年3月20日時点)
※ゴミ屋敷のような状態、特殊清掃が必要だと料金が変わります。
親の家の片付け費用は、間取りや物量など作業工数によって大きく異なります。
上記の表はあくまでも目安になり、生前整理や遺品整理、ごみ屋敷片付けなどケースによっても料金形態はさまざま。
正確な金額を知るためには、適切な業者複数社から相見積もりを取るのがおすすめです。
親の家を片付ける際に心がけたいポイント
親の家を片付ける前には、押さえておきたいポイントがあります。スムーズかつ効率的に作業を進めるためにも事前に把握しておきましょう。
なるべく早めに取り組む
親の家の片付けはなるべく早めに取り組むのが理想です。特に自力で片付ける場合、少なくない時間と労力がかかります。
親御さんがご存命の場合でも、急な怪我や病気で自宅のバリアフリー化などが必要になることもあるでしょう。いざという時に迅速に対応できるように備えておくと安心です。
まずは親としっかりコミュニケーションを取る
親御さんがご存命のうちに生前整理や実家を片付ける場合、まずはしっかりとコミュニケーションを取ることが重要です。
内閣府の調査によると、多くの高齢者が現在の住居に対して一定以上満足しているため、片付けに抵抗を感じるケースも少なくありません。
トラブルが起こらないように話し合ったうえで片付けを行いましょう。

親の意向を尊重する
実家の片付けは親御さんの意向を十分に尊重したうえで行います。実家はあくまで「親の家」なので子どもが独断で作業を進めるのはNGです。
子どもの判断だけで片付けを進めた結果、親御さんの価値観とすれ違い、揉め事に発展してしまうケースも少なくありません。親御さんの意向を尊重しながら取り組むことは非常に重要です。
実際に親の家を片付けた人の声
他界した親の家を片付けたケース(40代女性・埼玉県)
|
両親が他界した為、4DKの実家の片付けをお願いしました。 当初、姉妹で片付けようと思いましたが、どこから手をつければよいか途方に暮れ、プライムハートさんにご連絡しました。 見積もりの時点から丁寧な対応で、見ず知らずの父に手を合わせていただきました。 いろいろな関係の業者さんが出入りしていましたが、そんな気遣いをして下さったのはプライムハートさんだけでした。 当日までもこまめにご連絡を下さり、実際の当日も丁寧迅速な対応をしていただき本当に感謝の言葉しかありません。 最後には掃除まで行っていただき、気持ちよくお願いする事ができました。 皆さんのあたたかい気持ちと最後までやさしい言葉をかけて下さり、本当にお願いをして心からよかったと思っています。 人生の中でそうそうある事もない遺品整理ですが、自分の時もお願いしたいと思います。 この度は本当にありがとうございました。 |
出典:みんなの遺品整理掲載業者「プライムハート」口コミ・評判・実際の支払い金額
空き家になっていた親の家を片付けたケース(50代男性・兵庫県)
|
空き家になっていた実家の片付けをお願いしました。 口コミも良かったので問い合わせしたところすぐに見積もりにきてくれました。 綺麗にしていただきありがとうございます。 |
出典:みんなの遺品整理掲載業者「プライムハート」口コミ・評判・実際の支払い金額
施設入居をきっかけに親の家を片付けたケース(50代男性・新潟県)
|
急に父親が特別養護老人ホームに入ることになり生前整理をお願いすることになりました。 私は首都圏居住のため新潟の実家に何時も居る事は出来ないですが、ご担当の方にはとても親切に丁寧にご対応いただき満足度は120%以上です。 有難うございました。 |
出典:みんなの遺品整理掲載業者「お宅かたづけ隊」口コミ・評判・実際の支払い金額
物が増えすぎた親の家を片付けたケース(30代女性・栃木県)
|
実家に沢山ある不要品の山をどうしようかと困っていた所、お力を借りて整理と部屋の清掃をお願いしました。 使う物、使わない物一つ一つ確認しながら親身になって丁寧に作業していただいて本当に助かりました。家族だけではムリでした、、、。 部屋がスッキリし、よみがえって本当に良かったです。本当にありがとうございました。 |
出典:みんなの遺品整理掲載業者「遺品整理・特殊清掃アジャスト」口コミ・評判・実際の支払い金額
不用品の買取込みで親の家を片付けたケース(40代女性・茨城県)
|
実家の荷物を整理・不用品の処分および買い取れるものがある場合は買取希望で業者さんを探していました。 あらかじめ作業予定や時間スケジュールを伝えて頂けたのでとても助かりました。細かいところも確認いただきながらで非常に心強かったです。本当によかったです。 |
出典:みんなの遺品整理掲載業者「株式会社ワンステップサービス」口コミ・評判・実際の支払い金額
親の家を片付けた人の満足度はそれぞれ異なりますが、改善後の環境について好意的な意見が寄せられています。
業者に依頼すると、短時間で効率的に片付けが進むため、忙しかったり、遠方に住んでいたりする場合も親の家を片付けられます。
まとめ
親の家の片付けには、さまざまなメリットや把握しておくべきポイントがあります。
親御さんや親族とのトラブルを防ぐためにも、しっかりとコミュニケーションを取りながら進めましょう。
物の処分についてなど、親御さんの意見を尊重しながら片付けることが大切です。
「みんなの遺品整理」では、親の家の片付けを依頼できる優良業者を紹介しています。依頼者や親御さんの気持ちに寄り添った丁寧な作業を行う業者を厳選して掲載。
親の家の片付けをご検討中の方は「みんなの遺品整理」にご相談ください。
【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】
遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。
遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。
法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟。法規制を守り、遺品整理業務を真摯に行っている企業の優良認定、消費者保護のための遺品整理サービスガイドラインの制定もおこなっている。
【執筆者:みんなの遺品整理事務局】
東証プライム市場上場企業の株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営しています。2017年より業界最大級の遺品整理・実家の片付け業者の比較サイト「みんなの遺品整理」を運営し、全国で累計件数30,000人以上の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。
はじめての遺品整理でも、専門知識が豊富な相談員が中立な立場で、無料アドバイスをさせていただきます。大切な人の生きた証を残しつつ、気持ちよく次の世代へ資産や遺品を引き継ぐために、私たちは、お客様一人一人に最適なお手伝いができる情報提供・業者のご提案を致します。
ご実家のお片付けにお困りですか?
みんなの遺品整理では、全国881社の優良遺品整理業者から
複数業者の相見積もり・全国即日対応可能
お急ぎの方はお電話にてご相談ください!
通話無料
みんなの遺品整理 お客様相談窓口
0120-905-734受付時間 8:00~19:00 (土日祝も対応)
相談無料
- 複数見積もり可(最大3社)
- 買取対応などの相談も◎
- 即日・最速対応業者をご案内