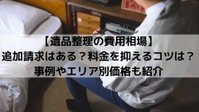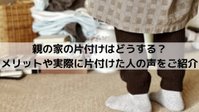相続の遺留分とは、相続人が確保できる最低限の遺産の取り分を指します。「遺産が予想より少なかった」など、相続にはさまざまな問題が伴うことも。そこで本記事では、相続遺留分の基本から計算方法や請求手続きまでを分かりやすく解説します。相続発生時の対応を明確にするためにも、ぜひ本記事を参考にしてください。

遺留分とは?
遺留分とは、相続人が確保できる最低限の遺産の取り分のことです。
遺産相続は、故人の遺志や遺言をもとに行われます。しかし故人の遺志に従うと、以下のように相続人が遺産を相続できない場合も発生します。
| 【遺言で相続ができない場合】 |
|---|
| ・遺言に、「財産1,000万のうち、妻と子供1人に50万円ずつ、残りは愛人に譲る」と書いてあるが、これだけでは遺族は安定した生活を送れない ・「財産1,000万を全額寄付する」という遺言が残っており、遺族が1円も遺産を受け取れない |
こういった状況は「遺留分の侵害」であるため、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を請求することができます。
遺留分を請求できる人は?
遺留分を請求することを「遺留分侵害額(減殺)請求」と言います。
この遺留分侵害額請求ができる人は「兄弟姉妹以外の法定相続人」と法律で定められており、具体的には以下のいずれかに当てはまります。
| ・配偶者 ・子 / 孫(代襲相続人) ・父母 / 祖父母(直系尊属) |
しかし遺留分侵害額請求ができる法定相続人であっても、以下のような方は請求ができません。
- 遺産相続を放棄した人
- 一定の事由により相続権を失った相続欠格者
遺留分を請求できる期限は?
また遺留分侵害請求の期限は、相続開始や減殺すべき贈与・遺贈があると知った日から1年、または相続開始時から10年以内と決められています。
この期間内を過ぎると、遺留分侵害請求権は時効によって消滅します。
遺留分の計算方法
では、遺留分はどのように計算したらよいのでしょうか?ここからは遺留分の計算方法について解説します。1人あたりの遺留分は、基本的に以下の式で計算できます。
| 遺留分=①遺産×②遺留分の割合×③法定相続分割合 |
また、子供が複数人いる場合と、両親が共に相続人である場合は、この割合をさらに人数で割ると1人分の額がでます。
| 遺留分÷子または親の人数=1人分の額 |
では、①、②、③のそれぞれの求め方を見てみましょう。
①遺産
遺留分の計算で対象となる財産は、生前に受けた贈与も含まれます。つまり、亡くなった際に1,000万の財産があり、なおかつ生前に故人から500万円を贈与されていた場合、1,500万円が遺留分の計算の対象となります。
②遺留分の割合
遺留分の割合は、以下の表に記載しているとおりです。
| 相続人 | 割合(権利者全員の割合の合計) |
|---|---|
| 配偶者のみ |
1/2 |
| 子どものみ | |
| 配偶者と子ども | |
| 配偶者と親 | |
| 親・祖父母(直系尊属)のみ | 1/3 |
相続人が直系尊属のみ以外の場合は、相続する遺産のうち1/2が遺留分となります。親や祖父母のみが相続人の場合は、遺産のうち1/3が遺留分です。
③法定相続分割合
相続人が1人の場合は遺留分の割合を1人で相続することができます。しかし相続人が複数の場合は、さらに遺産を分割する必要があります。
配偶者と子供が相続人の場合と、配偶者と親が相続人の場合の割合を以下にまとめました。

遺留分計算例1:配偶者と子供が相続人
仮に財産が2,000万円とし、相続人が配偶者と子供だった場合の子供の遺留分を計算してみましょう。

[①遺産]は 2,000万円とします。配偶者と子供を合わせた[②遺留分の割合]は全体の1/2です。また、配偶者と子供で分割するとき、子供の[③法定相続分割合]は1/2になります。
そのため、式に当てはめると…
| ①遺産 2,000万円×②遺留分の割合 1/2×③法定相続分割合 1/2=子供の遺留分 500万円 |
よって子供の遺留分は500万円になります。このように相続人が配偶者と子供で、かつ子供の人数が2人の場合、子供1人の遺留分は以下のようになります。
| 遺留分 500万円÷子供の人数 2人=1人の遺留分 250万円 |
遺留分計算例2:配偶者と親が相続人
次に、財産が6,000万円とし、相続人が配偶者と両親だった場合の両親の遺留分を計算してみましょう。

[①遺産]は 6,000万円です。配偶者と親を合わせた[②遺留分の割合]は全体の1/2です。配偶者と両親で分割するとき、両親の[③法定相続分割合]は1/3になります。
そのため、式に当てはめると…
| ①遺産 6,000万円×②遺留分の割合 1/2×③法定相続分割合 1/3=両親の遺留分 1,000万円 |
よって両親の遺留分は1,000万円になります。さらに父親のみの遺留分をもとめる場合は、両親の遺留分を父親と母親の二人で分割した額になります。
| 両親の遺留分 1,000万円÷親の人数 2人=父親の遺留分 500万円 |
そのため、父親の遺留分は500万円です。
遺留分を請求する方法
では、遺留分の侵害が発覚した際、どうやって請求すればいいのでしょうか。
遺留分を請求する相手は、遺言や生前贈与などによって遺産を受けとった人です。また、遺留分を請求するための特別な手続きがあるわけではありません。
相手方と話し合って、支払いに合意してもらえれば解決します。しかし、合意できなかった場合は裁判まで持ち込まれる場合もあります。
ここでは、相手に支払いに合意してもらうための流れについて紹介します。
①話し合い
まずは、支払いに合意してもらえるように請求する相手に話し合いを持ち掛けます。遺留分の支払いに納得してもらうことができれば、「遺留分侵害額についての合意書」を作成して支払いを行ってもらいます。
②調停
話し合いができない場合や、合意してもらえない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を持ち掛ける必要が出てきます。離婚などの際と同じでいきなり裁判に持ち込むことはできず、まずは調停で話し合います。
③裁判・訴訟
調停で話し合っても合意してもらえないという場合は、裁判に持ち込むことになります。「遺留分侵害額請求訴訟」を依頼すると、裁判所が遺留分の額を計算し相手に請求をします。
裁判に持ち込むことになった場合は、専門的な知識が必要になるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ
相続の遺留分は、相続人が確保できる最低限の遺産を守る重要な制度です。遺留分の請求手続きは期限が設けられており、計算方法や請求手順を理解することが必要になります。疑問や不明点がある場合、早急に対応しましょう。
「みんなの遺品整理」では、相続に関する相談にも対応可能な優良遺品整理業者を紹介中です。スムーズな遺品整理を実現するためにも、ぜひご検討ください。
【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】
遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。
遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。
法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟。法規制を守り、遺品整理業務を真摯に行っている企業の優良認定、消費者保護のための遺品整理サービスガイドラインの制定もおこなっている。
【執筆者:みんなの遺品整理事務局】
東証プライム市場上場企業の株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営しています。2017年より業界最大級の遺品整理・実家の片付け業者の比較サイト「みんなの遺品整理」を運営し、全国で累計件数30,000人以上の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。
はじめての遺品整理でも、専門知識が豊富な相談員が中立な立場で、無料アドバイスをさせていただきます。大切な人の生きた証を残しつつ、気持ちよく次の世代へ資産や遺品を引き継ぐために、私たちは、お客様一人一人に最適なお手伝いができる情報提供・業者をご提案します。