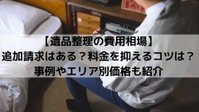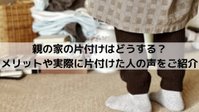家族が亡くなったらすることは多く、心理的な負担も小さくありません。葬儀の手配から役所への手続き、相続の流れまで、わかりやすく解説します。故人を見送るために役立つ情報なので、ぜひ本記事を参考にしてください。
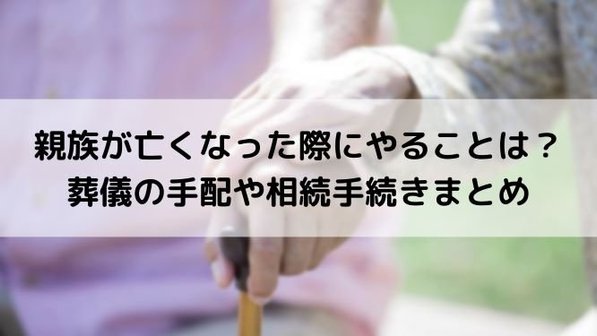
ご実家のお片付けにお困りですか?
みんなの遺品整理では、全国901社の優良遺品整理業者から
複数業者の相見積もり・全国即日対応可能
お急ぎの方はお電話にてご相談ください!
通話無料
みんなの遺品整理 お客様相談窓口
0120-905-734受付時間 8:00~19:00(土日祝も対応)
相談無料
- 複数見積もり可(最大3社)
- 買取対応などの相談も◎
- 即日・最速対応業者をご案内
やるべき葬儀の手続き、手配8つ

身内の方が亡くなったとき、葬儀手続きを行います。
葬儀関係の手続きはだいたい7日以内に行う必要があります。
やるべき事は以下の通り
1.葬儀会社を選ぶ
地元の葬儀社やネットで探すなどして、葬儀社を選ぶ必要があります。病院で無くなると葬儀会社から声をかけてくることも多いです。
2.遺体を搬送する
葬儀会社に連絡し遺体の搬送を依頼します。自宅や葬儀社の安置場所に搬送する手配を行います。葬儀社には搬送だけでも依頼し、あとでどこにお願するか決められます。
3.葬儀内容の打ち合わせ
葬儀会社との通夜、葬儀・告別式の打ち合わせを行います。喪主の選任、日時、場所などを決めます。
4.葬儀に関する周知
親戚、勤務先、関係者、近所の方に葬儀の周知を行います。
5.通夜
通夜を行います。
6.葬儀・告別式
葬儀・告別式を行います
7.火葬
葬儀・告別式が終わり次第、出棺し火葬場で火葬されます。
この時点で火葬許可証が必要となるため、事前に役所に届け出を行っておきます。
8.初七日(神道の場合は十日祭)
通常亡くなった日から数えて7日目に行う法要ですが、最近では葬儀の際に行うことも。神道の場合は多少異なってくるので、神社の方と確認するようにしましょう。
以上が亡くなってから初七日までの手続きです。
やるべき役所への手続き7つ

役所への届け出手続きはおおよそ14日以内に行う必要があります。
やるべき事は以下の通りです。
1.死亡届(7日以内に行う)
故人の死亡を認知した日より7日以内に提出します。死亡地か本籍地、住所地のいずれかの市区町村の役場にある戸籍・住民登録窓口で行います。
<必要書類>
医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、届出人は印鑑が必要
2.死体火・埋葬許可申請
死亡届と一緒に提出しましょう。必要書類も同じです。手続き後、火葬許可書が交付されます。
3.住民票の抹消届(14日以内に行う)
死後14日以内に、市区町村役場の戸籍・住民登録窓口で行います。
<必要書類>
届出人の印鑑、本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
これまでは必ず行う手続きを確認してきました。この先は、該当することが多い手続きをピックアップします。下記に該当する場合は、手続きを忘れずに行いましょう。
4.年金受給停止の手続
死亡後、 社会保険事務所、または市区町村役場の国民年金課などの窓口へ行き、速やかに行います。場合によっては遺族が「未支給年金の支給」を受けることができるので、その場合は別途手続きを行ってください。
<必要書類>
年金受給権者死亡届(添付書類として年金証書と、戸籍謄本など死亡の事実が証明できる書類)
5.介護保険資格喪失届
死後14日以内に、市区町村役場にある福祉課などの窓口で行います。
<必要書類>
介護保険証
6.世帯主の変更届(3人以上の世帯の世帯主であった場合)
死後14日以内に、市区町村役場の戸籍・住民登録窓口で行います。
<必要書類>
届出人の印鑑、本人確認できる証明書類
7.遺言書の検認(けんにん)
遺言書はあるが、公正証書ではない場合に、亡くなった方の住所地の家庭裁判所で行います。
<必要書類>
開封・閲覧していない遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本
やるべき相続の手続き8つ

相続関係の手続きは1年以内に行う必要があります。
1.金融機関への連絡
死亡後すぐに、名義の預貯金などの取引を止めるために金融機関へ連絡します。
2.生命保険金の受取
(故人が保険金受取人の場合、相続財産となるので相続確定後に請求)
死後2年以内に、契約していた保険会社で行います。
<必要書類>
保険証券、死亡保険金請求書、最後の保険料領収書、保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本、受取人の印鑑証明書、死亡診断書
3.相続人調査(遺言書がないとき)
相続人が自分達で話しあって遺産分割の方法を決めます。
4.相続財産の調査
被相続人の死亡後、自宅やネット銀行やネット証券、郵便物やなどを調べ、残高証明書の取得を行います。
5.遺産分割協議
相続人調査と相続財産の調査終了後、相続人すべてが集まって遺産分割の方法を決めます。
6.所得税の準確定申告
死亡から4カ月間以内に、故人の住所地にある税務署か勤務先で行います。
<必要書類>
死亡した年の1月1日~死亡日における所得の申告書、生命保険料の領収書、医療控除証明書類など
7.遺産分割協議書作成
8.相続税申告(相続財産が基礎控除額以下の場合必要なし)
死亡日の翌日から10カ月以内に、被相続人(故人)の住所地の税務署で行います。
<必要書類>
申告書、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票・住民除票、 全相続人の戸籍謄本・印鑑証明書など。
また、これらの手続きに限らず遺産分割の際に遺産分割審判や、相続財産を放棄する相続放棄、限定承認などの手続きが発生する場合があります。
まとめ
ご家族が亡くなったらすることは想像以上に多く、葬儀や相続に関する手続きなどは大きな負担になります。本記事の内容をあらかじめ把握しておくことで、いざという時も慌てずに対応できるでしょう。
遺品整理や付随する相続の手続きでサポートが必要な場合は「みんなの遺品整理」の利用がおすすめです。プロの業者に依頼することで時間や労力の軽減が期待できます。お悩みの際はぜひご相談ください。
【監修者:一般財団法人遺品整理士認定協会】
遺品整理業界の健全化を目的に2011年設立。
遺品整理士養成講座を運営し、認定試験・セミナー・現場研修などを実施している。
法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟。法規制を守り、遺品整理業務を真摯に行っている企業の優良認定、消費者保護のための遺品整理サービスガイドラインの制定もおこなっている。
【執筆者:みんなの遺品整理事務局】
東証プライム市場上場企業の株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(ライフルシニア)が運営しています。2017年より業界最大級の遺品整理・実家の片付け業者の比較サイト「みんなの遺品整理」を運営し、全国で累計件数30,000人以上の皆様からご相談・ご依頼をいただいております。
はじめての遺品整理でも、専門知識が豊富な相談員が中立な立場で、無料アドバイスをさせていただきます。大切な人の生きた証を残しつつ、気持ちよく次の世代へ資産や遺品を引き継ぐために、私たちは、お客様一人一人に最適なお手伝いができる情報提供・業者のご提案を致します。
ご実家のお片付けにお困りですか?
みんなの遺品整理では、全国901社の優良遺品整理業者から
複数業者の相見積もり・全国即日対応可能
お急ぎの方はお電話にてご相談ください!
通話無料
みんなの遺品整理 お客様相談窓口
0120-905-734受付時間 8:00~19:00(土日祝も対応)
相談無料
- 複数見積もり可(最大3社)
- 買取対応などの相談も◎
- 即日・最速対応業者をご案内